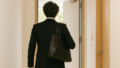社会人になって一人暮らしを始めたとき、最初に直面したのが「家事」の問題でした。
仕事で疲れて帰ってきた後に掃除や洗濯、食事の支度をするのは思った以上に大変で、つい後回しにしてしまうことも多かったです。
しかし、家事を後回しにすると部屋が荒れ、精神的にもだらけてしまい、悪循環に陥ることを痛感しました。
そこで、無理なく家事を習慣化するために、いくつかのシンプルなルールを設けることにしました。今回は、その実践例と効果について紹介します。
家事が続かなかった頃の悩み
仕事から帰るとクタクタで、家に着くとすぐにソファに倒れ込み、「今日はもう何もしたくない」という気分になっていました。
掃除も洗濯も先延ばしにし、週末になって一気にまとめてやろうとするものの、結局手がつけられずにさらに放置……。
部屋は荒れ、洗濯物は山積み、キッチンは洗い物だらけ。
そんな環境にいると、ますますやる気が削がれ、自己嫌悪に陥るという悪循環を繰り返していました。
このままではまずいと感じ、何とか家事を日常の中に組み込めないかと考えるようになりました。
家事を習慣化するために取り入れたシンプルなルール
1. 家事を「イベント」ではなく「作業」にする
以前は「掃除するぞ!」「洗濯するぞ!」と大げさに構えていたため、余計に腰が重くなっていました。
そこで、家事を特別なイベントではなく、日常の一部として捉えることにしました。
たとえば、
- 歯磨きのついでに洗面台をサッと拭く
- お湯を沸かしている間にシンクを軽く洗う
このように、生活の動線に家事を組み込むことで、自然と体が動くようになりました。
「ついで」にやる感覚にすると、心理的なハードルがぐっと下がります。
2. タスクを「超小分け」にする
「部屋を掃除する」というざっくりした目標だと、何から手をつけていいか分からずに結局手が止まってしまうことが多かったです。
そこで、タスクをできるだけ細かく分けるようにしました。
例:
- テーブルの上だけ片付ける
- ゴミを一袋だけまとめる
- 床の一角だけ掃除機をかける
一つ一つのタスクを小さく区切ることで、取りかかるハードルが低くなり、「やり始めれば意外とできる」という感覚が持てるようになりました。
3. 「毎日10分だけ」と決める
家事をやる時間を無理に長く取ろうとすると、忙しい日は続きません。
そこで「毎日10分だけ家事をする」とルールを決めました。
タイマーをセットして、その間だけ集中する。
終わったら、続きがあってもそこで一旦ストップ。
このルールを守ることで、「続けること」にフォーカスできるようになり、自然と家が整っていきました。
不思議なことに、10分だけと決めると始めやすく、しかもやっているうちに「もうちょっとだけやろうかな」と思うことも増えました。
始めるハードルを下げることが、結果的に家事量を増やすことにもつながったのです。
工夫を続けて感じた変化
これらのシンプルなルールを取り入れてから、家事が「特別なこと」ではなく、「日常の一部」になりました。
- 部屋がきれいだと気分がいい
- 週末にまとめてやる負担が減った
- 自己嫌悪に陥ることが少なくなった
何より、「できなかった自分」を責める回数が減り、自己肯定感が少しずつ高まっていったのが大きな変化でした。
また、家が整っていると、仕事から帰ってきたときの安心感が違います。
疲れていても、「とりあえずくつろげる空間がある」というだけで心が軽くなるのを実感しました。
完璧を目指さないことの大切さ
家事を習慣化する上で一番大切にしているのは、「完璧を目指さない」という考え方です。
多少ホコリがあっても、洗濯物が一日遅れても、大した問題ではありません。
「できるときに、できるだけやる」というスタンスを持つことで、精神的な負担がぐっと減りました。
頑張りすぎて続かなくなるよりも、ゆるくても続けられる方がずっと意味がある。
そう思うようになってから、家事に対する心のハードルが驚くほど低くなりました。
まとめ
社会人になって家事を習慣化するために取り入れたシンプルなルールは、
- 家事を「イベント」ではなく「作業」にする
- タスクを超小分けにする
- 毎日10分だけと決める
この3つだけです。
特別なテクニックや根性論ではなく、日々の中で無理なく続けられる工夫を積み重ねることで、生活は確実に変わりました。
これからも「完璧じゃなくていい、少しずつ」で家事を続けながら、自分にとって心地いい暮らしを作っていきたいと思います。
忙しい毎日の中でも、少しの工夫で暮らしは変えられる。
そう実感できたのが、何よりの収穫でした。